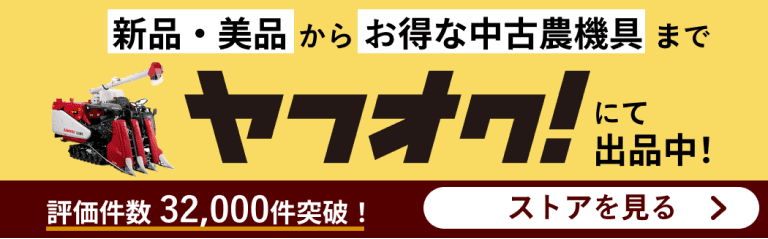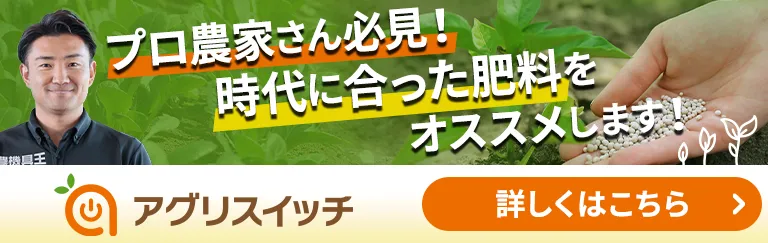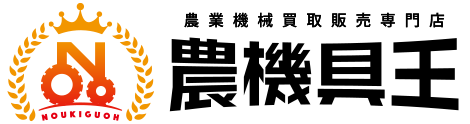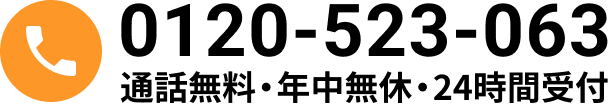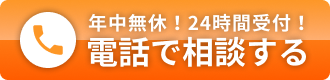- トラクターってどんな作業ができるの?
- そもそもトラクターって何?
トラクターのことを知りたいと思っても、なかなか情報が少ないですよね。
特に新規就農を考えている方は、トラクターで何ができるのか気になると思います。
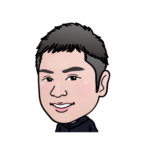
全国33店舗を構える農機具の販売と買取を行っている農機具王のWEB担当テノが書いていきます!
この記事ではトラクターの、概要、歴史、可能な作業、選び方をまとめました。
この記事を読めば
- トラクターについて全体像を理解できるようになります。
結論、トラクターの可能性を知れば、農作業の幅をもたせることができます。
それではどうぞ。
トラクターとは農作業の万能選手
トラクターとは、人の力では引っ張れないようなものを引く車の総称です。
作業機を付け替えて、様々な農作業に対応してくれる、農作業の万能選手とも言えるでしょう。
後ほど紹介しますが、作業機を切り替えれば、農作業のほとんどができてしまうのです!
トラクターの特徴的な構造
重たい作業機を後部につけて、牽引するので、前方にはウェイトがついてバランスが取られています。
作業機を装着できるのが一番特徴です。
PTOと呼ばれる作業機にエンジンの動力を転送する仕組みが用いられていて、牽引するだけではなく、作業機を動かすこともできます。
タイヤは、どのような土壌でも走行できるように、グリップ力の強い大きなタイヤです。
また履帯式のタイヤの物も流通しており、より力強く作業が進められるような工夫がされています。履帯式とは戦車のキャタピラーイメージしてください。
エンジンは高い負荷の作業を行うためにディーゼルエンジンが搭載。
ディーゼルエンジンは低燃費で高出力のものが使われています。
更に変速機で様々な作業に対応していますし、ROPSという運転者を保護する安全フレームなどもついているのです。
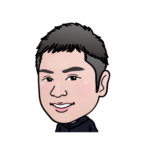
トラクターがなぜここまで高機能で便利になったのか、それはトラクターの歴史を紐解くとわかります!
トラクターの歴史
トラクターは、土壌を掘り起こす、鍬(くわ)や鋤(すき)、牛馬が牽引する犁(すき)が進化してきた物です。
それまで家畜の餌や人力がエネルギー源でしたが、石油が燃料となりました。
特に20世紀前半では、各国がこぞって開発しています。
第一次大戦の戦車は、農業用トラクターの履帯タイヤが発送で開発されています。
そのこともあってか第二次大戦中の戦車工場は、農業用トラクター工場が用いられたようです。
大型船やジェット機、インターネットやレトルト食品、四輪駆動車などは、全て戦争によって発展した文明ですが、農業用トラクターも戦争の歴史ともに発展してきました。
現在のトラクターの便利さは、このような背景で発展してきたのです。
トラクターの未来
21世紀では、無人型トラクターをGPS機能を用いて、自動運転で作業させるなど、スマート化が進んでいます。
現在、日本の農業は離農が増えていて、集落営農などの共同で農業に取り組みから、どんどん効率化の流れが加速しています。
そんな中で、クボタの130周年記念では、夢のトラクターが公開されました。
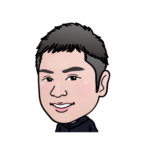
トラクター感が全くなくて、SF映画で登場しそうです!

また日本ニューホランド株式会社のレポートで、世界最大の農業機械展「アグリテクニカ2019」のフォトレポートがあるので、気になる方は読んでみてください。
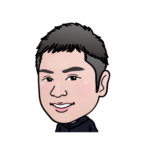
ここまでトラクターの概要について説明してきました。
次はトラクターがどれほどの万能選手なのか、実際にできる作業についてご紹介します。
トラクターでできる作業と作業機
トラクターでできる作業はこちら。
- 耕起(こうき)
- 代掻き(しろかき)
- 施肥(せひ)
- 消毒
- 畝立て(うねたて)
- マルチ
- 播種(はしゅ)
- 除雪
- 草刈り
これほどの作業が行えるのは、作業機があればの話なので、作業機の値段なども考慮して、何ができるのか確認してください。
それでは一つずつ作業と作業機の紹介をしてきます。
耕起(こうき)
耕起とは、土を耕すことです。掘り起こしたり返したりします。
目的としては以下の通りです。
- 土をほぐす
- 雑草の引き抜きや細断
- 土壌のかき混ぜ
- 乾燥の防止
- 鍬床をほぐす
農業においては植え付けの前に行う作業です。
・ロータリー
・プラウ
ロータリー


一般的にはロータリーを使うことがほとんどです。
特に水田の耕起ではロータリー1つで作業がすべて済ませることができます。
馬力の強くトラクターの作業が可能です。
プラウ


プラウはロータリーと違い、深く耕すことができます。
その分、抵抗が大きいので馬力の強いトラクターが必要です。
また耕起後に整地作業が必要になります。
代掻き(しろかき)
水の入った田んぼの土を砕いて平らにするのが代掻きです。
代掻きを行わないと、平ではないことで、稲が沈んだり、水が届かなくなってしまいます。
・代掻きハロー
・ロータリー
代掻きハロー


ハローは、代掻き専用なので、より平らにすることができます。
均平精度がたかくなるので、成長のムラなどにも効果があります。
道路通行時に車の邪魔になったり、車庫に収納しやすいということで、現在はおりたたみのハローが人気です。
ロータリー
代掻きはロータリーでも代用可能ですが、やはり代掻き専用のドライブハローには劣ります。
またロータリーで代掻きを行うには技術が必要とされているので、しっかり検討してください。
施肥(せひ)
施肥は直接農作物に影響を与える重要な作業です。
均一に散布する必要があります。
・ブロードキャスター
・肥料散布機
・マニュアスプレッダー
ブロードキャスター


2種類の散布方法があります。
1つはフリッカー式と呼ばれ、機械を振動させることが肥料を散布。
もう一つはスピンナー式。円盤を回転させて肥料を散布します。
肥料を広範囲に遠心力で飛ばし時間短縮する反面、均一性はやや劣ります。
肥料散布機


ブロードキャスターと比べて、散布範囲が狭いです。
時間がかかる反面、均一に散布することができます。
各メーカーで名前が違い、ライムソワー、グランドソワー、サンソワーなどがあります。
マニュアスプレッダー


肥料をほぐし均一に全面散布する機械です。
作業能率が高く、利用範囲も広く、よく利用されています。
消毒
農作物を連作していると、土壌の栄養が偏ったり、害虫が増加したりします。
そのために土壌消毒が必要です。
・ブームスプレーヤ
ブームスプレーヤ


トラクターに取り付けて、広範囲の消毒や除草剤を散布することができます。
畝立て(うねたて)


畝を立てると撥水性や通気性に効果があります。
根張りもよくなるので必要な作業です。
・培土機
マルチ


マルチとは畝をポリエチレンフィルムなどで多いことです。
土の乾燥や病気の伝染を防いだり、土の温度の調整ができます。
・マルチロータリ
播種(はしゅ)
種まきのことです。
・播種機
播種機


除雪


積雪の多い地域では除雪も大切な仕事です。
パワーのあるトラクターを使って行うこともできます。
・スノーラッセル
草刈り


トラクターに取り付けるタイプの草刈り機です。
・フレールモア
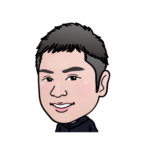
ここまでトラクターでできる作業を見てきました。
作業機の種類だけ様々な作業ができるトラクターはやはり農家には欠かせないことがご理解頂けたと思います。
次はトラクターを選ぶコツについてご紹介します。
トラクターを選ぶコツ
新規就農をする方は、トラクターの選び方も大事です。
ここでは、主要の国内トラクターメーカー4選と中古トラクターについてご紹介します。
国内主要トラクターメーカー4選
- クボタ
- ヤンマー
- イセキ
- 三菱マヒンドラ
まず上記の4メーカーから選べば間違いありません。
各メーカーの詳しい情報は以下の記事に記載しています。
中古トラクター
日本メーカーのトラクターは壊れにくいと評判が良いです。
海外などの新興国では日本の2〜30年前の年式のトラクターが高値で取引されています。
ただし、状態が良いものを探す必要があるので、きちんと状態を記載しているところから購入しましょう。
メルカリやヤフーオークションなどでは、破格の値段でトラクターが販売している場合があります。しかし、それはジャンク品などの可能性が高いです。
個人出品ではなく、きちんと販売元を確認してから購入してください。
まとめ
トラクターについて理解を深められたでしょうか。
とにかく万能なトラクター。作業機の付け方で様々な用途に使えます。
まずはどのような計画で農業するのか考えて、トラクターをご検討ください。
農機具王の買取サービスなら
私たちは以下のような体制で買取を行っております。
- 無料出張査定に対応!
- 24時間専門のオペレーターが親身になって電話対応いたします!
- 農機具の買取知識をこの公式ブログでご紹介
- よくあるご質問も完備
- 全国33箇所の買取店舗あり
- 買取実績豊富
- 販路はヤフーオークション、店舗販売、新興国への輸出があります
- お電話でどんなものが買取できるかご相談ください!まとめて買取可能です。
まずは買取業者の相見積もりをする業者として候補を入れて頂けたら幸いです。
その他のオススメ記事